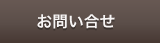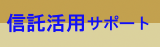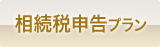平成24年9月号
日ごろ税務の仕事しておりますと、クライアントから戸籍と相続の関係をよく尋ねられます。そこで、今回は戸籍とは何か・・という原点に立って、相続との関係を述べてみたいと思います。
1.戸籍とは・・・・・・・
◆戸籍とはいったい何なの・・・・・・・・・
日本に戸籍制度ができたのは明治5年です。明治以来、日本には家(いえ)制度があり、これは明治31年に民法で制定された日本の家族制度です。その家の代表者を戸主(こしゅ)といいます。江戸時代の家父長・家督制度が基となっています。この戸主とその家族を一つの家に帰属させて、その家の構成員を役所の帳簿に登録したものが戸籍です。
暗記したい専門用語
①【戸主(こしゅ)】:
家族の代表者。一番偉い人で通常は一家の父親です。
②【戸籍(こせき)】:
戸籍の戸(こ)は戸主(こしゅ)の戸なので戸籍(こせき)と読 みます。本籍のことです。
③【筆頭者(ひっとうしゃ)】:
家族の代表者。通常は父親で戸籍簿の最初の1行目に記 載記されており戸籍簿のインデックス・索引名のようなものです。
◆戸籍は何のためにあるの・・・・・
第一に、本人が生きている証拠、即ち、確かに日本人として存在していることの証明のためです。 第二に、婚姻関係・親子関係などの親族関係の確認のためで、家庭裁判所での訴訟や調停、審判の手続きに利用されますが、最も多いのは相続関係(父が死亡 → 母・子供が父の財産を相続するため)の証明のためです。 即ち、亡くなった人の財産を法律上相続できる相続人を特定するための証明書の役割をはたします。
暗記したい専門用語
④【法定相続人(ほうていそうぞくにん)】:
法定相続人とは、民法で規定された相続の権利がある人を さし、法律でその範囲と順番が決められています。 死亡し被相続人(=相続される人)の財産を相続できる権利がある 人のことです。
◆戸籍謄本と戸籍抄本との違いは・・・・
戸籍謄本(とうほん)とは、戸籍に記載されている家族全員の存在を証明する書面で 「全部事項証明書」ともいいます。例えば、本籍地以外の役所へ届出る結婚届・離婚届・転籍届 および相続手続きでこれらの書面が必要です。 戸籍抄本(しょうほん)とは戸籍に記載されている家族の一部の個人の存在を証明する書面で「一部事項証明書」ともいいます。例えば、海外旅行を計画した長女がパスポートの申請に必要なこの抄本には長女以外の家族は記載されていません。
◇ブレイク・タイム◇
自分の本籍地のある区役所に、自分のUSBメモリーを持って行けば、戸籍謄本・戸籍抄本は役所のPCからUSBメモリーに落としてもらえますか?
→ NOです。紙の謄本・抄本しかもらえません。個人情報の漏えい・窃用・ウイルス感染が怖いですからね。
◆戸籍をコンピューター化するとは・・・
平成6年から法律が変わり、市区町村では従来の読みづらい手書きの縦書の紙戸籍から、データベース化された綺麗な横書のコンピューター戸籍に変わりました。
このことを「改製(かいせい)」といいます。戸籍が改製される前(平成6年以前)の結婚・離婚や配偶者の死亡は改製後のコンピューター戸籍に移記(写し替えること)されません。
従って、改製前の戸籍も取り寄せないと、改製前の家族の身分関係がわからないことになります。この改製前の戸籍を改製原戸籍といい、その謄本の取り寄せに1通750円かかります。
暗記したい専門用語
⑤【紙(かみ)戸籍】:
書面・紙で役所に登録・管理されている戸籍をいいます。
⑥【コンピューター戸籍】:
役所のPCで磁気ディスクにメモリーされている戸籍のことです。
⑦【改製(かいせい)】:
平成6年に紙戸籍からコンピューター戸籍に変更されたことをいいます。 尚、市区町村役場によっては、切り替え作業が膨大であることを理由に改製が済んでない役場もあります。例えば世田谷区役所は平成17年になってはじめて改製されました。
⑧【改製原戸籍(かいせいはらこせき)】:
平成6年に書き換えられる前のそれまでの元の戸籍を「改製原戸籍」といい、書き換えられた新しい戸籍は「現在戸籍、現戸籍(げんこせき)」という 現在の戸籍を見ても、書き換え以降のことしか載っていないために、書き換えられる前の戸籍(改製原戸籍)も見ないと身分関係が正確にわかりません。
◆戸籍には何が書いてあるの・・・・・
記載事項の主なものは下記の通りです。
・家族ひとりひとりの氏名と本籍
・誕生日
・戸籍に入籍した原因と年月日
・父・母の氏名と【続柄(ぞくがら:長女・長男・養子・・)】
・他の戸籍から入ってきた人(養子など)の戸籍の表示
・他の戸籍へ出て行った人(結婚・離婚など)、亡くなった人は戸籍簿から除籍されます 等
暗記したい専門用語
⑨【除籍(じょせき)】:
結婚して転籍した人、死亡した人は、 その戸籍から除籍 (じょせき) されたといい、役所のPC画面上の戸籍簿に 「除籍」とINPUTされてしまいます。
2.相続人と戸籍との関係は・・・・
◆亡くなった人の遺産を誰が相続するの・・
生存配偶者(夫又は妻)とその子供は最優先の相続人です。 配偶者が死亡した場合を考えてみましょう。
配偶者のどちらかが死亡したとします。人が死亡するとその人の財産が相続されますが、死亡した人を被相続人と呼びます。 生存している配偶者(夫が死亡の場合は妻)を中心に考えた場合、まず、未亡人となった妻が必ず相続人となります。 そして、あとの順番は、原則として、配偶者に子供がいる場合、子供(直系卑属)が第1順位となり、子供がいない場合、被相続人の実の両親(直系尊属)が第2順位となります。 実の両親が共に他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位となります。 即ち、子供がいれば第2順位以下(両親・兄弟姉妹)には相続分はなく、妻と子供たちだけが相続人となります。 子供がいない、子はすでに死亡している 又は 孫もいない場合、両親のどちらか 又は 祖父母のどちらかが生きていれば、第3順位(兄弟姉妹)には相続分はなく、生きている被相続人の両親・祖父母が相続人となります。 子供もいない孫もいない両親・祖父母も共に他界している場合にのみ、被相続人の実の兄弟姉妹に相続分がめぐってくることになり、生きている兄弟姉妹が相続人となります。
以上の登場人物(被相続人・未亡人・子供たち・両親・兄弟姉妹などなど)の「親族相関図」を作成するには、被相続人の遺産を相続できる人を特定する必要があり、そのために「戸籍(身分関係の証明書)」が必ず必要となるわけです。
暗記したい専門用語
⑩【被相続人(ひそうぞくにん)】 :
死亡した人のことです。被相続人の配偶者は無条件で相続人となれます。
⑪【相続の第1順位】:
被相続人の子供たち 又は 死亡した子供の孫たちで この孫を代襲(だいしゅう)相続人と呼びます。また、子・孫たちを総称して「直系卑属(ひぞく)」といいます。
⑫【相続の第2順位】:
被相続人の実の両親 又は 祖父母で、これらを総称して「直系尊属(そんぞく)」といいます。
⑬【相続の第3順位】:被相続人の実の兄弟姉妹です。
◆人が死亡したら戸籍の何が必要・・・・・・
人が死亡して相続が発生した場合には、被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。我が国の戸籍制度はきめ細かく整っており、人の身上や親族関係がほぼ完ぺきに網羅されていますから、被相続人が生まれてから亡くなるまでの一生の戸籍(揺りかごから墓場まで)を、途切れなく連続的に取り寄せて相続人を確定するわけです。
3.最後に・・・・
ご自分の戸籍を本籍地のある市区町村役場へ出向いて取り寄せてみてはいかがでしょうか。
現在お住まいの地区から本籍地のある市区町村役場が遠方の場合には、郵送による戸籍の請求もできます。この場合、先ずは、最寄りの役所・出張所で「郵送請求用の戸籍交付請求書」の 用紙を入手し必要事項を書き込みます(不明な点は役所の係員に尋ねてください。)。
①上記申請書 ②役所の手数料(戸籍謄本なら1通450円、郵便局で定額小為替を購入) ③切手を貼った返信用封筒、④更に本人確認として運転免許証、又は、健康保険証のコピー1通、以上の①②③④を同封して本籍地のある役所へ郵送すれば、2週間程度で興味深いご自分の戸籍謄本が返送されてきまのでぜひ一度試してみてください。