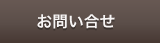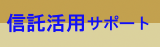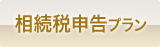平成27年7月号
債務と相続の関係
「借金をすると相続税が少なくなる。」という話をよく聞きます。被相続人の債務は相続税計算上控除できるからです。しかし、ただ借金をすればいい訳ではありません。一方、債務は相続人が引き継ぎます。ないと思っていた債務を突然引き継がなければならなくなることもあります。相続と債務の関係についてまとめてみたいと思います。
◆なぜ借金があると相続税が少なくなるのか
民法は「相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896条)」と規定しています。つまり、相続人は財産だけでなく、債務も引き継がなければならないのです。そこで相続税においては、相続人の受けた利益に課税すべく、財産だけでなく債務も承継した場合には、その差額、つまり正味財産を課税対象としています。しかし、借入金を増やせば、単純に相続税が少なくなるのかというとそうではありません。例えば他人から5,000万円を借りても、そのままでは現金が5,000万円増えているはずだからです。その現金を何かに使わなければなりません。不動産を購入したり建築したりすると、相続税評価額は一般的にその代金よりが低くなるため、昔からよく節税対策として利用されています。できる限り借入金額と不動産の相続税評価額の差を大きくするために、空地にアパートを建築したり、最近ではタワーマンションの一室を購入したりするのです。
◆相続税計算上控除できる債務とは?
控除される債務は、被相続人死亡の際に存在する確実なものに限られます。次のような債務が控除の対象です。
| 借入金 | 住宅ローン、アパートローン、個人からの借入金、同族会社からの借入金など |
| 固定資産税 住 民 税 |
これらの税金は1月1日に納税義務が確定します。納期限未到来であっても死亡時に未払いものはすべて控除できます。 |
| 所 得 税 消 費 税 |
前年分の確定申告をする前に死亡した場合はもちろん、死亡した年分の所得税や消費税も控除の対象となります。 |
| 未払医療費 介 護 費 |
死亡後に病院等に支払う入院費用などは控除の対象となります。 |
| 水道光熱費 | 電気、ガス、水道、電話など後払いの公共料金で、被相続人の死亡前の使用に伴うものは控除の対象となります。 |
| クレジットカード | 死亡前の使用分は控除の対象となります。 |
逆に、遺産分割のための弁護士費用や相続税申告のための税理士報酬などは、相続人等の費用であり被相続人の債務ではないため控除の対象とはなりません。
◆相続人以外に債務を承継させるなら負担付遺贈
被相続人の債務は、相続人又は包括受遺者が承継した場合のみ控除することができます。したがって、たとえば相続人でない孫にアパートを特定遺贈する場合などは注意が必要です。アパートローンや預り敷金などもその孫に引き継がせたいところですが、仮に引き継いだとしても相続税計算上それら債務を控除することはできないのです。このような場合に有効な方法が負担付遺贈です。「アパートローン及び預り敷金を負担することを条件にアパートを孫に遺贈する」という遺言を作成します。負担付遺贈は、負担前の財産価額から負担額を控除した価額が取得した財産の価額とされるため、実質的に控除できてしまうのです。
◆保証債務に要注意!
被相続人は借金とは無縁だったと安心してはいけません。被相続人が生前に他人や会社の保証人になっていた場合、相続人は原則としてこの保証債務も引き継がなければならないのです。一方、相続税の計算上は、保証債務は確実な債務ではないため控除の対象とはなりません。主たる債務者が弁済不能状態で実際に相続人が肩代わりをした上で、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合に限り控除することが許されています。
◆被相続人の債務から逃れるには放棄、限定承認
被相続人の遺産が債務超過である場合や債務保証の可能性が高い場合などは、「相続放棄」または「限定承認」を検討することになります。相続放棄すれば、相続人は財産も債務も一切引き継がないことになります。しかし、どうしても欲しい財産がある場合や、どのような債務があるか不明な場合などは放棄が躊躇されることもあるでしょう。そのような場合には限定承認が選択肢となります。ただし、限定承認をすると被相続人が財産を譲渡したものとみなされるため、結果的に債務の額よりも財産の額の方が大きかった場合には、相続人は相続税だけでなく譲渡所得税も負担しなければならなくなる場合があるので慎重な判断が求められます。とはいってもゆっくり考えることもできません。放棄又は限定承認をするには、原則として相続から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないのです。