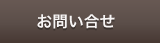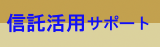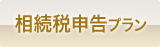平成27年9月号
社宅にすれば手取りが増える
「社宅制度」というと、福利厚生を目的に比較的大きな会社が導入するもの、と考えている方も多いのではないでしょうか。実はどのような規模の会社であっても、社宅制度を導入することで大きなメリットを享受することができます。社宅といっても従業員寮の建築を勧めるわけではありません。いわゆる借上げ社宅で十分なのです。家族経営のような小規模な会社でも構いません。
◆住宅手当制度ではなく社宅制度を!
住宅に関する従業員への補助には、大別して「住宅手当」と「社宅」があります。住宅手当は、家賃などの補助として従業員の給与に上乗せして支給される金銭です。これに対し社宅は、会社が従業員のために用意した住宅で、通常安価で貸し出されます。つまり、住宅手当は給与にプラスされるのに対し、社宅は家賃相当額が給与からマイナスされることになります。そのためどちらの制度を導入するかにより、所得税や社会保険料の額に違いが生じるのです。住宅手当を支給すれば給与の額が増えるため、所得税や社会保険料の負担も増えてしまいます。同時に会社が負担する社会保険料も増加します。社宅制度なら同じ効果で、税金や社会保険料への影響を抑えることができるのです。
<具体例>
基本給 38万円
家 賃 15万円(うち7.5万円を会社が補助)
| 住宅手当 | 社 宅 | |||
| 月 給 | 年 収 | 月 給 | 年 収 | |
| 基本給 | 380,000 | 4,560,000 | 380,000 | 4,560,000 |
| 住宅手当 | 75,000 | 900,000 | - | - |
| 支給合計 | 455,000 | 5,460,000 | 380,000 | 4,560,000 |
| 社会保険料 | 69,037 | 828,444 | 55,818 | 669,816 |
| 雇用保険料 | 2,275 | 27,300 | 1,900 | 22,800 |
| 所得税等 | 35,500 | 426,000 | 22,900 | 275,500 |
| 住民税 | 35,600 | 427,400 | 29,400 | 353,700 |
| 社宅家賃 | - | - | 75,000 | 900,000 |
| 控除計 | 142,412 | 1,709,144 | 185,018 | 2,221,816 |
| 差引支給額 | 312,588 | 3,750,856 | 194,982 | 2,338,184 |
| 住宅家賃 | 150,000 | 1,800,000 | - | - |
| 手元残金 | 162,588 | 1,950,856 | 194,982 | 2,338,184 |
上記の例では、従業員の最終的な手取り額に年間で40万円近い差が生じます。また会社としても社会保険料の負担に年間で約16万円の差が生じますので、従業員数が多い会社ほどその違いは歴然となります。
◆一定額以上の社宅家賃を負担すること
いくら社宅といっても、役員や従業員に無償や低額家賃で貸付けてしまうと、税務上、現物給与とみなされ課税対象となりますので注意が必要です。本人が負担すべき社宅家賃は、役員、従業員別に次のように定められています。
・従業員の場合・・・通常の賃借料Aの50%相当額以上
|
通常の賃借料A(月額)=(家屋の固定資産税課税標準額×0.2%) +(12円×家屋の総床面積÷3.3㎡) +(敷地の固定資産税課税標準額×0.22%) |
一般的に上記算式で計算した通常の賃借料Aは、実際の賃借料よりも低くなります。しかし借上げ社宅の場合、大家さんから固定資産税課税標準額を聞き出すことは現実的には難しいかもしれません。その場合には単純に実際の賃借料の50%以上を従業員から給与天引きしておけばほぼ問題ないでしょう。
・役員の場合・・・上記、通常の賃借料A
ただし、家屋の床面積が132㎡(木造以外は99㎡)を超える場合は次の算式で計算した金額となります。
|
○会社所有の社宅の場合の通常の賃借料(月額) {(家屋の固定資産税課税標準額×12%(木造家屋以外は10%)) +(敷地の固定資産税課税標準額×6%)}×1/12・・・B ○借上げ社宅の場合の通常の賃借料(月額) 「実際の賃借料×50%」と「上記算式B」のいずれか多い額 |
さらに、家屋の床面積が240㎡を超えるような豪華な役員社宅については、一般の相場賃料が通常の賃借料とされます。
また、役員や従業員が会社に支払う社宅家賃の額が厚生労働大臣の定める住宅家賃の標準価額を下回る場合は、その下回る額は現物給与として社会保険の対象となります。
◆他にはどんなメリット、デメリットがあるか
社宅制度を導入すると、税金や社会保険料以外にも次のようなメリットがあります。
・採用上の有利性や従業員のモチベーションの向上。
・会社が継続して借り上げれば、従業員の入れ替りの都度、敷金、礼金や原状回復費を支払う必要がない。
・代表者などは、会社が購入した社宅に住むことで、減価償却費や固定資産税、維持修繕費などを会社の経費にできる。
その反面、次のようなデメリットも存在します。
・会社は物件の管理、事務手続きが必要となる。
・従業員は住まいまで会社に管理されることになり、転居もし辛い。