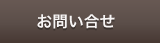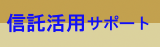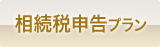平成29年5月号
使いやすくなった?非上場株式の納税猶予
非上場会社のオーナーにとって株式は経営に必要不可欠な財産です。しかし、会社が成長すればするほど株価が上昇し、後継者の事業承継時の税負担は大きなものとなります。時には経営維持に支障をきたし会社存続が困難になることも。
そこで円滑な事業承継をサポートすべく平成21年に創設されたのが「非上場株式の納税猶予制度」で、何度かの税制改正を重ねて使い勝手も改善されてきました。
◆相続なら80%、贈与なら100%の納税猶予
先代経営者から後継者が相続により取得した株式について納税猶予の適用を受けると、その非上場株式に対する相続税の80%相当額の納税が猶予されます。
先代から後継者が贈与により株式を取得し納税猶予の適用を受けると、その贈与税の全額の納税が猶予されます。
※ただし、相続後又は贈与後の後継者の所有株式数が発行済株式の3分の2に達するまでの株式に限られます。
◆相続税の納税猶予の適用を受けるには?
相続後、中小企業者であることなどの会社の要件や、以下の先代経営者、後継者の要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
<先代経営者の要件>
|
(1) 以前その会社の代表者であったこと (2) 相続直前に同族関係者で50%超の株式を保有し、後継者以外の同族関係者の中で筆頭株主であること |
<後継者の要件>
|
(1) 相続直前で役員(60歳未満の場合を除く)であり、相続から5か月後までに代表者に就任していること (2) 同族関係者で50%超を有し、その中で筆頭株主であること |
◆贈与税の納税猶予の適用を受けるには?
相続税の納税猶予と同様に、贈与後、会社の要件や、以下の先代経営者、後継者の要件を満たしていることについて経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
<先代経営者の要件>
|
(1) 贈与以前にその会社の代表者であったこと (2) 贈与時までに代表者を退任していること (3) 贈与直前に同族関係者で50%超の株式を保有し、後継者以外の同族関係者の中で筆頭株主であること |
<後継者の要件>
|
(1) 贈与時に20歳以上の代表者であること (2) 同族関係者で50%超を有し、その中で筆頭株主であること |
◆納税猶予が取り消される場合(納付)
納税猶予の適用を受けた後継者が死亡した場合など一定の場合には、納税猶予されていた相続税や贈与税は免除されます。
その反面、申告期限後5年以内に次のようなケースに該当することとなった場合には、猶予されていた税額を利子税と併せて納付しなければなりません。
|
(1) 代表権がなくなった場合 (2) 5年間平均で雇用の8割を維持できなかった場合 (3) 同族関係者の議決権数が50%以下となった場合 (4) 同族関係者の中で筆頭株主でなくなった場合 |
◆平成29年度税制改正では何が変わった?
(1) 雇用維持要件の緩和
申告期限後5年平均で雇用を8割維持しなければなりません。改正前は従業員4人以下の小規模な会社は1人でも減らせば8割を下回ってしまうことから非常に高いハードルでした。
29年4月1日以降は1人未満の端数は切り捨てて判定されることとなったため、1人の減少は認められることになりました。(1人がゼロになるのはダメ。)
<相続時4人 → 5年平均3人>・・・4人×80%=3.2人
(改正前)4人必要 ∴×
(改正後)3人でOK ∴○
(2) 贈与税の納税猶予取消し時の税負担を軽減
贈与税の納税猶予は、万が一取消しになってしまうと高額な贈与税とその利子税を納付しなければなりません。このリスクの大きさからに贈与税の納税猶予の利用が進みませんでした。
平成29年度以降は、贈与時に相続時精算課税制度を選択して納税猶予の適用を受けることができるようになりました。取消しになっても2,500万円控除後の金額の20%の贈与税を納付し、先代の死亡時に相続税に課税し直されるため、理論上贈与税負担はなくなります。
<評価額1億円の株式が取り消された場合>
(改正前)贈与税4,800万円+利子税
(改正後)贈与税1,500万円+利子税(相続時に相続税が課税され、贈与税1,500万円は控除される。)
(3) 贈与税猶予期間中でも上場を目指せる
贈与税の納税猶予を受けた後、先代経営者が死亡した場合には、猶予されていた贈与税が免除された上で贈与を受けた株式について相続税が課税されます。通常、この相続税についても相続税の納税猶予が適用されるのですが、贈与後、相続までの間に上場するなど中小企業でなくなっている場合には適用されませんでした。
29年以降は、非上場会社であること及び中小企業者であることの要件が撤廃され、会社の成長が阻害されることがなくなりました。